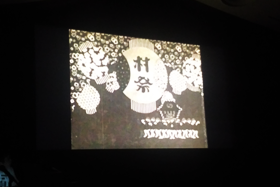一
一
『モアナ 南海の歓喜』公開記念公開講座
ロバート・フラハティとドキュメンタリーの変容
第1回 【ドキュメンタリーに向かってー
ロバート・フラハティの映画人生の始まり】
『モアナ 南海の歓喜』公開記念公開講座。第一回目は、映画評論家の村山匡一郎先生をお招きし、映画監督ロバート・フラハティの人生についてお話しいただきました。
話はフラハティの生い立ちから始まり、どのようにして映画監督になったかを追っていきます。
フラハティは幼いころから父の仕事についてまわるなかで、ネイティブ・アメリカンやイヌイットなど、他文化の人びとと触れ合いながら育ちました。
フラハティが初めて映画を制作したのは、ハドソン湾ベルチャー諸島の調査探検の中で撮影した『極北のナヌーク』。
はじめは調査の記録映像から始まった作品でした。
イヌイットの生活を映したこの作品は、公開されると大きな反響を呼びます。
村山先生によると、この映画の特徴は、従来の枠組には収まらない新たな作風を確立していたこと。
フラハティはこの映画の中に、劇映画的に創作した部分と、実際に起きた出来事を記録した部分とを織り交ぜていたのです。
のちに、このあらたな手法が「ドキュメンタリー」と名指されることになるというのですが、現代の私達のドキュメンタリー観とはかなり違っていてとても驚きました。
講座の後半では、フラハティの『24DollersIsland』と、別監督の作品『Manhatta』が比較上映されました。
いずれも1920年代のマンハッタン島をテーマにした短編作品なのですが、この二作品には大きな違いがあるといいます。
『Manhatta』には、マンハッタン島の1日を追うという物語が背後にあるのに対し、フラハティの作品では風景のカットがまとまりなく繋がれているだけ。
どこか散漫としています。
しかし、そのかわりフラハティの作品は、ビルから出る煙や、ゆったりと水面を走る船を雄大に描いています。
この違いは一体なにを意味するのでしょうか。
私はそこに、フラハティ作品に共通する何かが潜んでいるような気がしました。
鈴木大樹